わがまち再発見(第2回長瀬の歴史散策会)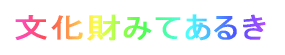 (長瀬地区Ⅰ) |
2004.3.21 長瀬の歴史散策会の案内文書 講師の谷戸実先生から、資料1が届きました。掲載が遅れすみません。 資料1 rekisisansakukai-siryou1.pdf へのリンク(谷戸実先生著作) 資料2(小粒がやについて。本校の保護者の大矢さんのご提供) 拡大写真の頁へ |
  |
  |
| 国津神社(長瀬)手水鉢 文政2(1819)年と石灯籠。 | 長瀬の国津神社境内でお話を聴く参加者の皆さん。 |
  石灯籠 貞享2(1685)年(芭蕉「野ざらし紀行」の 年)神社より、天然記念物「左巻きがや」へ至る道 を望む。 |
  基準標本木だった小粒榧。説明は地主の大矢さん。 |
  |
  |
| 3本ある左巻榧 | 長瀬橋周辺:伊賀で最古の道標 宝暦元年三月 (1751) |
  |
  |
| 庚申信仰の庚申碑 延宝8(1680)年、貞享3(1686)年 | 長瀬局前周辺:伊勢信仰の常夜灯 明治元年 歴史を刻む下り松碑。後方に周辺マップが。写真をクリック。 |
  国津神社参道。 不動寺境内。 |
  |
| 当日の散策ルートの道順通りに撮影写真を掲載し ました。 |
六地蔵石とう(桃山時代16世紀後半頃のものか) |
  |
  |
| 鎌倉時代の古い五輪塔。厄よけ石(名張の昔話) | 不動寺境内の譲り葉(ゆずりは)の木と、本堂の額。 |
| 詳細は、後日、講師の谷戸実先生から資料を メールで頂けることになり、届き次第掲載します。 |
講師の谷戸先生、主催者の皆様、ありがとうございました。次回が楽しみです。 |
| Copyright: Nagase Elementary School - Nabari City / Mie Prefecture /Japan 2003-2004All rights reserved. |