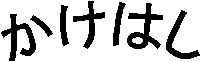
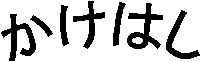
先月2月22日(土)、育友会主催の人権・同和教育研修会がありました。今年は、啓発アニメビデオ「天気になあれ」を視聴し、その後小グループに分かれて、活発な話し合いが行われました。
ビデオを観た感想としては、「教科書が無償配布になった経緯を、はじめて知った。」というお声がありました。また、話し合いの中では、「間違ったことを伝えていくのではなく、大人達がしっかり子ども達に伝えていかなくてはならない。」というご意見や、「正しい理解をすることの大切さを再確認した。」、「おのおの自分の認識を変えることで差別問題をなくし、人権の尊重が出来ると思う。」等など、貴重なお声を聞かせていただけました。
以上の話し合いや、その後お寄せいただいたアンケートを、今後の本校の人権・同和教育に生かしていきたいと思います。ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。
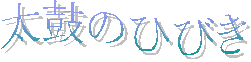
「ドンドコ、ドンドコ」「ドンツク、ドンツク」・・・。これらのひびきを聞けば、自然に身が軽くなるいろいろな太鼓。今でも祭りの獅子舞や神社の奉納太鼓、そして「天正みだれ太鼓」のように、町おこしの一つとなっているようなものもあります。
太鼓作りには、先祖より秘伝とされた専門的な技術を要します。そして、武具などの皮革産業にたずさわった被差別部落の人々の伝統技術が受け継がれています。命あるものを殺し、その皮革を材料にした太鼓作りの人々は、永く差別を受けながらも技術と誇りを持って作り続けてきました。太鼓の内側に製作者の名前を記してあるのが多いのもその表れだろうと考えられます。古老への聞き取りによりますと、名張市では大正時代の末まで作り続けたようです。牛皮を求め、それを灰汁につけ、毛を抜き、脂肪をとり、なめすというていねいな作業の結果、太鼓に張る皮が出来上がります。干してある皮に触れてもしかられたほど、ていねいに取り扱っていたそうです。
太鼓のひびきは、大音響の演奏の中で、赤ちゃんがすやすや寝てしまったという話を聞くほど、力強さとともに安らぎを覚える音ともいえます。これは動物の命をいただき、工夫をこらしてあらたな命を吹き込まれた「命の音」であるとも言えます。